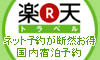上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
最新作です!
⇒悪の組織でサクセス! 乳魂の痛快出世巨乳フェチ小説、『揉ませてよオレの正義2』! 2013年5月17日発売! アマゾンで予約中!
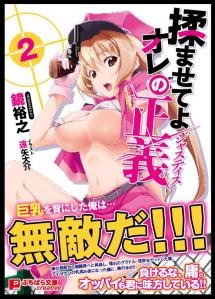
⇒原作者自らのノベライズ『巨乳ファンタジー2』発売! 2012年9月28日発売!


⇒なぜ、アニメや漫画は表現規制を受けるのか? なぜ、オタクや腐女子は叩かれるのか? そこには、性と資本主義の問題が横たわっている。婚活とオタクの問題はつながっているのだ。表現規制が全国的に強化されようとしている今こそ必要な、オタクのための知的防衛本。
⇒起承転結は役に立たない!? スランプにはどう対処するの? どうやってマーケットを理解するの?……などなど、技術的な面も精神的な面も細かくサポート。全24講義、400頁オーバー。「これ1冊あれば他の本はいらない」と読者に言わしめたゲームシナリオの決定版。同人ゲーム制作者は勿論、ラノベ作家志望者にもバイブルになります。

⇒抜きゲーなのに面白い!? エロゲー批評空間で、抜きゲーにもかかわらず評価80点の高得点! 「これがエロゲーだ」とユーザーに言わしめた、2009年ベスト抜きゲー。

![【送料無料】高1ですが異世界で城主はじめました [ 鏡裕之 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6729%2f9784798606729.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6729%2f9784798606729.jpg%3f_ex%3d80x80) 【送料無料】高1ですが異世界で城主はじめました [ 鏡裕之 ] |
⇒悪の組織でサクセス! 乳魂の痛快出世巨乳フェチ小説、『揉ませてよオレの正義2』! 2013年5月17日発売! アマゾンで予約中!
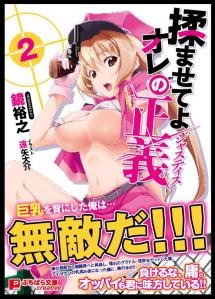
⇒原作者自らのノベライズ『巨乳ファンタジー2』発売! 2012年9月28日発売!


⇒なぜ、アニメや漫画は表現規制を受けるのか? なぜ、オタクや腐女子は叩かれるのか? そこには、性と資本主義の問題が横たわっている。婚活とオタクの問題はつながっているのだ。表現規制が全国的に強化されようとしている今こそ必要な、オタクのための知的防衛本。
 非実在青少年論 価格:1,890円(税込、送料別) |

⇒抜きゲーなのに面白い!? エロゲー批評空間で、抜きゲーにもかかわらず評価80点の高得点! 「これがエロゲーだ」とユーザーに言わしめた、2009年ベスト抜きゲー。

コンテンツ文化史学会第2回例会に参加してきました。
場所は、芝浦工業大学豊洲キャンパス研究棟5階大会議室。椅子が凄くステキでした。
テーマは、「ライトノベルと文学」。
文学部卒の血が疼きます(笑)。ちなみにプログラムは以下の通り。
●大島丈志「ライトノベルにおける日本近代文学の受容」
ライトノベルに近代文学作品が引用されたり中心的なガジェットになったりしている、特に宮沢賢治が絡んでいるというお話。中心的に取り上げられたのは、野村美月の文学少女シリーズです。
宮沢賢治は、『注文の多い料理店』の公告で、自分の読者対象は「少年少女期の終わり頃からアドレッセンス中葉」と書いていたようです。つまり、12~20才ってことね。また、秋枝美保氏の意見として、宮沢賢治の再評価=受容が始まるのは、1970年代の終わりであると、ということが紹介されていました。
あとで、大島先生とは少しお話をしました。その中で、いくつか申し上げたことがあります。
・なぜ近代文学の中で最も宮沢賢治が一番引用されるのか?
ライトノベルは、美少女ムーブメントの流れの中で生まれたものです。
70年代末までは、たとえば漫画の世界では、「性愛の対象=大人」「性愛の非対象=少女」と区別されていました。でも、70年代末から、思春期の少女も、性愛と恋愛の対象として描かれるようになります。その運動が、ササキバラゴウ氏の言う、美少女ムーブメントです。
美少女ムーブメントには、思春期の性愛と思春期の恋愛が含まれています。したがって、美少女ムーブメントの産物――その後にアニメも、アダルトアニメも、美少女ゲームも、そしてライトノベルにも、思春期の性愛と思春期の恋愛が折り込まれています。つまり、秋葉系エンターテインメントにとって、思春期的なものというのは、非常に中心的な、重要的な要素なんですね。
先の大島先生の説明にもあった通り、宮沢賢治は、自分の読者を思春期の少年少女に設定しています。その分、宮沢賢治の作品はライトノベルと重なっている部分が多く、ライトノベルに引用しやすいのだろうと思います。
ただ、宮沢賢治が引用されているからといって、近代文学がライトノベルで受容されているかというと、そう言い切るにはかなりの慎重さが必要です。お題目が「ライトノベルにおける日本近代文学の受容」となっていたのは、恐らくCM的な目的で「近代文学」と風呂敷を広げたのだと思いますが、CM的にではなく、真面目に言おうとすると、さらに議論の積み重ねが必要でしょう。
論理学の基本で、小集団に当てはまることを大集団に演繹できない、つまり、大集団にも当てはまると言うことができないというのがあります。この場合、小集団は宮沢賢治。大集団は、近代文学です。宮沢賢治が受容されるということは充分言い得るけれど、近代文学が受容されるとは、まだ言えないのではないかな、と個人的には感じています。
・なぜ、宮沢賢治を作品に引用するのか?
実は『BOIN SAGAブラバスター』(青心社文庫)の中に、ほんの少しだけ宮沢賢治がでてきます。淫魔に襲われた主人公の頭の中に、なぜか「あめゆじゅとてちてけんじゃ」という言葉が流れるというものです。非常に不真面目な引用なので、100%考察には値しません(笑)。
でも、文学の引用については、ぼくも経験があります。物語に深みを与えるために、文学ヤ哲学を引用するんですね。
小説と、ライトノベルという区分があります。大塚英志式に言うと、小説とキャラクター小説です。
小説は、生の人間の姿や生のありさまを描く、自然主義的リアリズムです。つまり、現実通りというわけです。
対してキャラクター小説(ライトノベル)は、まんが・アニメ的リアリズムが基盤です。わかやすい、平面的なキャラクター。記号性が強く、深みのないぺっこんたなキャラクター。そして、まんがやアニメで行われるようなアクションや現実。女の子が男を蹴ったら、男が飛んでいって星になっちゃうとかね。そういうまんが・アニメ的リアリズムです。
わかりやすい分、楽しみは増しますが、その分、マイナスポイントも表れます。記号的な平面的なキャラクターの場合、深みを出すのが難しいんですね。生や死といったハードなテーマに踏み込もうとすると、平面的なキャラクターがお芝居できる範囲を越えてしまうんですね。それを踏み越えてお芝居をやらせると、今度はキャラクターを離れて人間に近づいていって、深刻になってしまう。結果、お客さんが忌避するものになってしまう。 もちろん、編集さんからストップがかかる確率も上がります。シリアスなドラマを描くために深みを増そうとすると、キャラクターの背景も物語も、どんどん深刻になって、ライトノベルで表現するには難しいものになってしまうのです――相当の分量が用意されている美少女ゲームでは、もう少し難易度が低いのかもしれませんが。
だから、作品に深みを増すため、そしてキャラクターでは演じきれない深みの部分を補完するため、文学作品を引用するということを、作者レベルでは行っているようにぼくは感じています。
●井上乃武「コンテンツ横断的テクスト受容の試み-児童文学からライトノベルへ」
論の基本=スタートになったのは、小沢正という児童文学作家のファンタジー論です。
曰く、近代になって社会が子供を尊重せざるを得なくなり、子供には子供の世界があることが発見されるようになった。その発見から生まれたのが、ファンタジーである。子供は、下部構造的には学校という空間に閉じ込められ、上部構造的には、童心の世界に閉じ込められた。たとえていえば、現実には悪漢を追いかけえない世界。その、悪漢を追いかけえな世界がファンタジーを生み出す。
しかし、生み出したファンタジーによって、子供たちは、悪漢を追いかけえない世界から目を背けてしまっているのではないか。ならば、悪漢を追いかけえない世界に対して目を向かせるべきではないか。作品の中でファンタジー世界を死滅させることによって、現実に見開かせるべきではないか。
以上が、小沢正氏の議論です。その議論を軽く説明した後、児童文学作品の中から、ゲーム世界を舞台にして、現実に目を開かせるように書かれた作品(ファンタジーの死滅を狙った作品)が紹介されました。その後、東浩紀のゲーム的リアリズムの話に移行。
ゲーム的リアリズムについては、ぼくの方から補っておきます。間違っている部分があるかもしれませんが、ゲーム的リアリズムは、美少女ゲームから着想されたリアリズムです。
ゲームの場合、複数の物語が存在し、複数のエンディングが存在します。ある子のルートをプレイしていてバッドエンドにたどり着いても、選択肢を選びなおせばハッピーエンドにたどりつく。さらに別の選び方をすれば、ハーレムエンドもありうる。 したがって、現実は、複数化されています。つまり、複数の現実が考えられている。このように、現実が複数存在するというリアリズムのあり方を、東浩紀はゲーム的リアリズムと呼んでいます。
ゲーム的リアリズムは、大塚英志の言うまんが・アニメ的リアリズムとは少し違っています。まんが・アニメ的リアリズムは、深みのある人間の代わりに平面的なわかりやすい記号としてのキャラクターが描かれ、まんが的な表現やまんが的なリアリティのあり方で物語が描かれています。
ゲーム的リアリズムは、そのまんが・アニメ的リアリズムの世界から、複数的世界に踏み込んだものとして捉えられています。
井上氏は、ゲーム的リアリズムに比べると、児童文学が行ったファンタジーの死滅は古くさく思えると指摘してから、反駁を試みます。児童文学の場合、特にファンタジー世界の死滅を狙う作品には、世界の実際の作り手=創造者という存在がある。その創造者の問題を、東浩紀は忘れているのではなかろうか。
若干不正確な部分もありますが、以上が井上氏の議論です。
テーマとしては興味深かったのだけれど、まだ未完成の論という感じがしました。恐らく、これからどんどん煮詰めていかれるのだろうと思っています。ともあれ、児童文学を知らない自分にとっては、貴重な知識をいただけた機会でした。
ぼく個人的には、自然主義的リアリズム/まんが・アニメ的リアリズム⇒ゲーム的リアリズムという系譜の中では、児童文学は古いタイプのものだろうと思っています。でも、だからといって価値がないわけではない。新しいタイプだからといっていいわけでもない。子供の世界では、ゲーム的リアリズムの世界はまだ形成されていなくて、自然主義的リアリズムのみが存在しているのかもしれません。だとすれば、その世界は自然主義的リアリズムで描かれることになるのでは? という感じがしています。
井上氏の議論の中でぼくが気になったのは、創造者の問題でした。ぼくには、それはオイディプスの三角形のように見えてしまうんですね。
創造者が父親で、世界が母。そして、主人公がぼく=子供。オイディプス三角形。
母という世界を離脱して、現実に帰還するという話。世界を子宮と読み替えると、さらにわかりやすいかもしれません。児童文学の読者を考えると、作品内に両親のシンボルが入り込む、つまり、オイディプス的になるのは、自然な要請なのでしょう。
でも、ライトノベルでは、オイディプスの三角形はあまり関与していないように感じています。秋葉系エンターテインメントでは、父親が不在というのは非常に多いんですね。どうかすると、母親がいない場合だってあります。主題はパパ-ママ-ぼくという三角形の枠組みではなく、自我と性の世界に向かっている感じを受けます。
ちなみにぼくが関わった『パンドラの夢』では、ループする世界をつくったのは、みんなの願望です。ヒロインたちの願望であり、そして看護ロボットの願望です。創造者の問題は示されていますが、それは父親ではありません。オイディプスの三角形を脱しています。
ぼく個人は、児童文学とライトノベルは重ならないんじゃないか、と思っています。
ライトノベルを含めた秋葉系エンターテインメントって、セクシュアリティの問題を内包しているんですね。秋葉系エンターテインメントのお客さんって、性役割への不適合で苦しんでいる方が多いようにぼくは感じるんですね。
第二次性徴を迎えると、男性は大人のオスとしての性役割を、女性は大人のメスとしての性役割を負わなきゃならなくなります。そこでうまく性役割を演じるようになって、自分で伴侶を見つけて、自分で金を稼げるようになる。それが資本主義の要請ですが、その要請に応じようとした時に、うまく行かなくてセクシュアリティが傷ついてしまう子たちがいる。傷ついてしまうと、思春期の開始ともに成長を始めたばかりの男性性や女性性の発育が止まってしまう。オス年齢、メス年齢が非常に低い状態のままストップしてしまう。でも、性欲や性的ファンタジーなどの性的なものは、年齢を重ねるとともに人生の中で存在度と重要度を増していきます。
秋葉系エンターテインメントには、そういう人のために性的な部分をいたわり受け止めつつ、性的ファンタジーに応えていくという部分があるように感じます。それは、男性読者だけでなく、女性読者に対してもです。
けれども、児童文学のターゲットは、第二次性徴以前の子供たちです。性的なものは、恐らく、ほとんど含まれていないのではないか、とぼくは思っています。だとすれば、児童文学は、オタクの子たちのニーズを満たさないだろうし、児童文学とライトノベルが融合することもありえないのではないか。
ただ数十年前に比べて、今の子たちは発育が早くなっています。たとえば、女の子の場合、小学6年生の時点で半分が初潮を迎える計算になっています。となると、小学校の高学年から性的な時代に入る子たちもいるわけで、そういう子たちがライトノベルを読むようになるというのは、充分ありうることだな、と思います。ぼく自身は、ライトノベルや秋葉系エンターテインメントの研究には、それを受容する人たちのセクシュアリティや性役割の問題がもっとクローズアップされてもいいのではないか、もっとベースになってもいいのではないか、と考えています。読者のメンタリティを切り離した議論では、恐らく秋葉系文化の深部にはたどりつけないでしょう。
●山中智省「揺れ動く「ライトノベル」-ジャンル形成の現在」
ぼくが一番聞きたかったお題目です。山中さんは、横浜国立大学の大学院生。
出版月報からライトノベルに関する抜粋をしてくれていて、それが資料的に非常に興味深かったです。活字だけでライトノベルを評価していいのか、イラストも評価対象として含めるべきではないのか……と、ライトノベルと表紙カバー(イラスト)の関係にも踏み込もうとしていて、個人的にはその姿勢には好感を持ちました。持ったからこそ、あとで質問させていただきました。ぼくの質問は以下の通りです。
1.イラストは非常に主観的なものであり、なおかつ、萌え絵は習得しなければ弁別できないものである。たとえば、50代のオジサンだと、ほとんどの萌え絵は同じように見える。日本人が、イギリス人とドイツ人とアメリカ人の区別がつかないのと同じ状態。そういう現実がある中で、どうやってイラストに対する客観的な評価を打ち立てていくのか。絵に描いた餅になりはすまいか。
2.カバー表紙となると、非ラノベ以外の小説でも、カバーが存在し、それがセールスの重要ポイントとなっている。『ノルウェイの森』の大ヒットは、赤と緑の表紙がなければなかったという声もある。ラノベのイラストを分析したとしても、「同じことが普通の小説でも言えるじゃない」ということになってしまう。一般小説のカバー表紙との比較論も、論の完成度を高めるには必要ではないか。
学会の後は、豊洲駅近くの居酒屋で懇親会でした。あまり集団単位の飲み会は得意ではありませんが、非常に楽しかったです。出席してよかったな、と思える学会でした。
場所は、芝浦工業大学豊洲キャンパス研究棟5階大会議室。椅子が凄くステキでした。
テーマは、「ライトノベルと文学」。
文学部卒の血が疼きます(笑)。ちなみにプログラムは以下の通り。
というわけで、それぞれに対するぼくの感想と要約です。司会:七邊信重
13:00-13:40 大島丈志「ライトノベルにおける日本近代文学の受容」
13:40-14:20 井上乃武「コンテンツ横断的テクスト受容の試み-児童文学からライトノベルへ」
14:20-14:30 休憩
14:30-15:10 山中智省「揺れ動く「ライトノベル」-ジャンル形成の現在」
15:10-15:20 休憩
15:20-16:20 総合討論
●大島丈志「ライトノベルにおける日本近代文学の受容」
ライトノベルに近代文学作品が引用されたり中心的なガジェットになったりしている、特に宮沢賢治が絡んでいるというお話。中心的に取り上げられたのは、野村美月の文学少女シリーズです。
宮沢賢治は、『注文の多い料理店』の公告で、自分の読者対象は「少年少女期の終わり頃からアドレッセンス中葉」と書いていたようです。つまり、12~20才ってことね。また、秋枝美保氏の意見として、宮沢賢治の再評価=受容が始まるのは、1970年代の終わりであると、ということが紹介されていました。
あとで、大島先生とは少しお話をしました。その中で、いくつか申し上げたことがあります。
・なぜ近代文学の中で最も宮沢賢治が一番引用されるのか?
ライトノベルは、美少女ムーブメントの流れの中で生まれたものです。
70年代末までは、たとえば漫画の世界では、「性愛の対象=大人」「性愛の非対象=少女」と区別されていました。でも、70年代末から、思春期の少女も、性愛と恋愛の対象として描かれるようになります。その運動が、ササキバラゴウ氏の言う、美少女ムーブメントです。
美少女ムーブメントには、思春期の性愛と思春期の恋愛が含まれています。したがって、美少女ムーブメントの産物――その後にアニメも、アダルトアニメも、美少女ゲームも、そしてライトノベルにも、思春期の性愛と思春期の恋愛が折り込まれています。つまり、秋葉系エンターテインメントにとって、思春期的なものというのは、非常に中心的な、重要的な要素なんですね。
先の大島先生の説明にもあった通り、宮沢賢治は、自分の読者を思春期の少年少女に設定しています。その分、宮沢賢治の作品はライトノベルと重なっている部分が多く、ライトノベルに引用しやすいのだろうと思います。
ただ、宮沢賢治が引用されているからといって、近代文学がライトノベルで受容されているかというと、そう言い切るにはかなりの慎重さが必要です。お題目が「ライトノベルにおける日本近代文学の受容」となっていたのは、恐らくCM的な目的で「近代文学」と風呂敷を広げたのだと思いますが、CM的にではなく、真面目に言おうとすると、さらに議論の積み重ねが必要でしょう。
論理学の基本で、小集団に当てはまることを大集団に演繹できない、つまり、大集団にも当てはまると言うことができないというのがあります。この場合、小集団は宮沢賢治。大集団は、近代文学です。宮沢賢治が受容されるということは充分言い得るけれど、近代文学が受容されるとは、まだ言えないのではないかな、と個人的には感じています。
・なぜ、宮沢賢治を作品に引用するのか?
実は『BOIN SAGAブラバスター』(青心社文庫)の中に、ほんの少しだけ宮沢賢治がでてきます。淫魔に襲われた主人公の頭の中に、なぜか「あめゆじゅとてちてけんじゃ」という言葉が流れるというものです。非常に不真面目な引用なので、100%考察には値しません(笑)。
でも、文学の引用については、ぼくも経験があります。物語に深みを与えるために、文学ヤ哲学を引用するんですね。
小説と、ライトノベルという区分があります。大塚英志式に言うと、小説とキャラクター小説です。
小説は、生の人間の姿や生のありさまを描く、自然主義的リアリズムです。つまり、現実通りというわけです。
対してキャラクター小説(ライトノベル)は、まんが・アニメ的リアリズムが基盤です。わかやすい、平面的なキャラクター。記号性が強く、深みのないぺっこんたなキャラクター。そして、まんがやアニメで行われるようなアクションや現実。女の子が男を蹴ったら、男が飛んでいって星になっちゃうとかね。そういうまんが・アニメ的リアリズムです。
わかりやすい分、楽しみは増しますが、その分、マイナスポイントも表れます。記号的な平面的なキャラクターの場合、深みを出すのが難しいんですね。生や死といったハードなテーマに踏み込もうとすると、平面的なキャラクターがお芝居できる範囲を越えてしまうんですね。それを踏み越えてお芝居をやらせると、今度はキャラクターを離れて人間に近づいていって、深刻になってしまう。結果、お客さんが忌避するものになってしまう。 もちろん、編集さんからストップがかかる確率も上がります。シリアスなドラマを描くために深みを増そうとすると、キャラクターの背景も物語も、どんどん深刻になって、ライトノベルで表現するには難しいものになってしまうのです――相当の分量が用意されている美少女ゲームでは、もう少し難易度が低いのかもしれませんが。
だから、作品に深みを増すため、そしてキャラクターでは演じきれない深みの部分を補完するため、文学作品を引用するということを、作者レベルでは行っているようにぼくは感じています。
●井上乃武「コンテンツ横断的テクスト受容の試み-児童文学からライトノベルへ」
論の基本=スタートになったのは、小沢正という児童文学作家のファンタジー論です。
曰く、近代になって社会が子供を尊重せざるを得なくなり、子供には子供の世界があることが発見されるようになった。その発見から生まれたのが、ファンタジーである。子供は、下部構造的には学校という空間に閉じ込められ、上部構造的には、童心の世界に閉じ込められた。たとえていえば、現実には悪漢を追いかけえない世界。その、悪漢を追いかけえな世界がファンタジーを生み出す。
しかし、生み出したファンタジーによって、子供たちは、悪漢を追いかけえない世界から目を背けてしまっているのではないか。ならば、悪漢を追いかけえない世界に対して目を向かせるべきではないか。作品の中でファンタジー世界を死滅させることによって、現実に見開かせるべきではないか。
以上が、小沢正氏の議論です。その議論を軽く説明した後、児童文学作品の中から、ゲーム世界を舞台にして、現実に目を開かせるように書かれた作品(ファンタジーの死滅を狙った作品)が紹介されました。その後、東浩紀のゲーム的リアリズムの話に移行。
ゲーム的リアリズムについては、ぼくの方から補っておきます。間違っている部分があるかもしれませんが、ゲーム的リアリズムは、美少女ゲームから着想されたリアリズムです。
ゲームの場合、複数の物語が存在し、複数のエンディングが存在します。ある子のルートをプレイしていてバッドエンドにたどり着いても、選択肢を選びなおせばハッピーエンドにたどりつく。さらに別の選び方をすれば、ハーレムエンドもありうる。 したがって、現実は、複数化されています。つまり、複数の現実が考えられている。このように、現実が複数存在するというリアリズムのあり方を、東浩紀はゲーム的リアリズムと呼んでいます。
ゲーム的リアリズムは、大塚英志の言うまんが・アニメ的リアリズムとは少し違っています。まんが・アニメ的リアリズムは、深みのある人間の代わりに平面的なわかりやすい記号としてのキャラクターが描かれ、まんが的な表現やまんが的なリアリティのあり方で物語が描かれています。
ゲーム的リアリズムは、そのまんが・アニメ的リアリズムの世界から、複数的世界に踏み込んだものとして捉えられています。
井上氏は、ゲーム的リアリズムに比べると、児童文学が行ったファンタジーの死滅は古くさく思えると指摘してから、反駁を試みます。児童文学の場合、特にファンタジー世界の死滅を狙う作品には、世界の実際の作り手=創造者という存在がある。その創造者の問題を、東浩紀は忘れているのではなかろうか。
若干不正確な部分もありますが、以上が井上氏の議論です。
テーマとしては興味深かったのだけれど、まだ未完成の論という感じがしました。恐らく、これからどんどん煮詰めていかれるのだろうと思っています。ともあれ、児童文学を知らない自分にとっては、貴重な知識をいただけた機会でした。
ぼく個人的には、自然主義的リアリズム/まんが・アニメ的リアリズム⇒ゲーム的リアリズムという系譜の中では、児童文学は古いタイプのものだろうと思っています。でも、だからといって価値がないわけではない。新しいタイプだからといっていいわけでもない。子供の世界では、ゲーム的リアリズムの世界はまだ形成されていなくて、自然主義的リアリズムのみが存在しているのかもしれません。だとすれば、その世界は自然主義的リアリズムで描かれることになるのでは? という感じがしています。
井上氏の議論の中でぼくが気になったのは、創造者の問題でした。ぼくには、それはオイディプスの三角形のように見えてしまうんですね。
創造者が父親で、世界が母。そして、主人公がぼく=子供。オイディプス三角形。
母という世界を離脱して、現実に帰還するという話。世界を子宮と読み替えると、さらにわかりやすいかもしれません。児童文学の読者を考えると、作品内に両親のシンボルが入り込む、つまり、オイディプス的になるのは、自然な要請なのでしょう。
でも、ライトノベルでは、オイディプスの三角形はあまり関与していないように感じています。秋葉系エンターテインメントでは、父親が不在というのは非常に多いんですね。どうかすると、母親がいない場合だってあります。主題はパパ-ママ-ぼくという三角形の枠組みではなく、自我と性の世界に向かっている感じを受けます。
ちなみにぼくが関わった『パンドラの夢』では、ループする世界をつくったのは、みんなの願望です。ヒロインたちの願望であり、そして看護ロボットの願望です。創造者の問題は示されていますが、それは父親ではありません。オイディプスの三角形を脱しています。
ぼく個人は、児童文学とライトノベルは重ならないんじゃないか、と思っています。
ライトノベルを含めた秋葉系エンターテインメントって、セクシュアリティの問題を内包しているんですね。秋葉系エンターテインメントのお客さんって、性役割への不適合で苦しんでいる方が多いようにぼくは感じるんですね。
第二次性徴を迎えると、男性は大人のオスとしての性役割を、女性は大人のメスとしての性役割を負わなきゃならなくなります。そこでうまく性役割を演じるようになって、自分で伴侶を見つけて、自分で金を稼げるようになる。それが資本主義の要請ですが、その要請に応じようとした時に、うまく行かなくてセクシュアリティが傷ついてしまう子たちがいる。傷ついてしまうと、思春期の開始ともに成長を始めたばかりの男性性や女性性の発育が止まってしまう。オス年齢、メス年齢が非常に低い状態のままストップしてしまう。でも、性欲や性的ファンタジーなどの性的なものは、年齢を重ねるとともに人生の中で存在度と重要度を増していきます。
秋葉系エンターテインメントには、そういう人のために性的な部分をいたわり受け止めつつ、性的ファンタジーに応えていくという部分があるように感じます。それは、男性読者だけでなく、女性読者に対してもです。
けれども、児童文学のターゲットは、第二次性徴以前の子供たちです。性的なものは、恐らく、ほとんど含まれていないのではないか、とぼくは思っています。だとすれば、児童文学は、オタクの子たちのニーズを満たさないだろうし、児童文学とライトノベルが融合することもありえないのではないか。
ただ数十年前に比べて、今の子たちは発育が早くなっています。たとえば、女の子の場合、小学6年生の時点で半分が初潮を迎える計算になっています。となると、小学校の高学年から性的な時代に入る子たちもいるわけで、そういう子たちがライトノベルを読むようになるというのは、充分ありうることだな、と思います。ぼく自身は、ライトノベルや秋葉系エンターテインメントの研究には、それを受容する人たちのセクシュアリティや性役割の問題がもっとクローズアップされてもいいのではないか、もっとベースになってもいいのではないか、と考えています。読者のメンタリティを切り離した議論では、恐らく秋葉系文化の深部にはたどりつけないでしょう。
●山中智省「揺れ動く「ライトノベル」-ジャンル形成の現在」
ぼくが一番聞きたかったお題目です。山中さんは、横浜国立大学の大学院生。
出版月報からライトノベルに関する抜粋をしてくれていて、それが資料的に非常に興味深かったです。活字だけでライトノベルを評価していいのか、イラストも評価対象として含めるべきではないのか……と、ライトノベルと表紙カバー(イラスト)の関係にも踏み込もうとしていて、個人的にはその姿勢には好感を持ちました。持ったからこそ、あとで質問させていただきました。ぼくの質問は以下の通りです。
1.イラストは非常に主観的なものであり、なおかつ、萌え絵は習得しなければ弁別できないものである。たとえば、50代のオジサンだと、ほとんどの萌え絵は同じように見える。日本人が、イギリス人とドイツ人とアメリカ人の区別がつかないのと同じ状態。そういう現実がある中で、どうやってイラストに対する客観的な評価を打ち立てていくのか。絵に描いた餅になりはすまいか。
2.カバー表紙となると、非ラノベ以外の小説でも、カバーが存在し、それがセールスの重要ポイントとなっている。『ノルウェイの森』の大ヒットは、赤と緑の表紙がなければなかったという声もある。ラノベのイラストを分析したとしても、「同じことが普通の小説でも言えるじゃない」ということになってしまう。一般小説のカバー表紙との比較論も、論の完成度を高めるには必要ではないか。
学会の後は、豊洲駅近くの居酒屋で懇親会でした。あまり集団単位の飲み会は得意ではありませんが、非常に楽しかったです。出席してよかったな、と思える学会でした。
最新作です!
⇒悪の組織でサクセス! 乳魂の痛快出世巨乳フェチ小説、『揉ませてよオレの正義2』! 2013年5月17日発売! アマゾンで予約中!
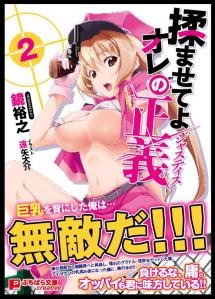
⇒原作者自らのノベライズ『巨乳ファンタジー2』発売! 2012年9月28日発売!


⇒なぜ、アニメや漫画は表現規制を受けるのか? なぜ、オタクや腐女子は叩かれるのか? そこには、性と資本主義の問題が横たわっている。婚活とオタクの問題はつながっているのだ。表現規制が全国的に強化されようとしている今こそ必要な、オタクのための知的防衛本。
⇒起承転結は役に立たない!? スランプにはどう対処するの? どうやってマーケットを理解するの?……などなど、技術的な面も精神的な面も細かくサポート。全24講義、400頁オーバー。「これ1冊あれば他の本はいらない」と読者に言わしめたゲームシナリオの決定版。同人ゲーム制作者は勿論、ラノベ作家志望者にもバイブルになります。

⇒抜きゲーなのに面白い!? エロゲー批評空間で、抜きゲーにもかかわらず評価80点の高得点! 「これがエロゲーだ」とユーザーに言わしめた、2009年ベスト抜きゲー。

![【送料無料】高1ですが異世界で城主はじめました [ 鏡裕之 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6729%2f9784798606729.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f6729%2f9784798606729.jpg%3f_ex%3d80x80) 【送料無料】高1ですが異世界で城主はじめました [ 鏡裕之 ] |
⇒悪の組織でサクセス! 乳魂の痛快出世巨乳フェチ小説、『揉ませてよオレの正義2』! 2013年5月17日発売! アマゾンで予約中!
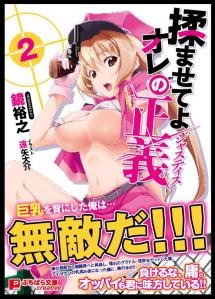
⇒原作者自らのノベライズ『巨乳ファンタジー2』発売! 2012年9月28日発売!


⇒なぜ、アニメや漫画は表現規制を受けるのか? なぜ、オタクや腐女子は叩かれるのか? そこには、性と資本主義の問題が横たわっている。婚活とオタクの問題はつながっているのだ。表現規制が全国的に強化されようとしている今こそ必要な、オタクのための知的防衛本。
 非実在青少年論 価格:1,890円(税込、送料別) |

⇒抜きゲーなのに面白い!? エロゲー批評空間で、抜きゲーにもかかわらず評価80点の高得点! 「これがエロゲーだ」とユーザーに言わしめた、2009年ベスト抜きゲー。

TRACK BACK
TB*URL
想定外の小説からスタート!
小説総合情報サイト? ノベリポ! 2009-10-21-Wed 21:47
小説総合情報サイト? ノベリポ! 2009-10-21-Wed 21:47
【本田直之さん初の小説!】「走る男になりなさい」を読みました!:マインドマップ的読書感想文 想定外の小説ってどんなんでしょうね。 そのキャッチで読みたいわ。 asahi.com(朝日新聞社):「忙しくて」本読めぬ30代 4人に1人「1カ月0冊」 - 社会 忙しくて本が読め [続きを読む]
| ホーム |